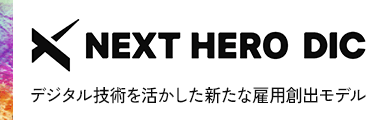第10回 【前編】今こそ、発達障害に対する知識が求められている

Road to IX
〜 就労困難者ゼロの未来へ 〜
編集者・ライター 黒坂 真由子氏
VALT JAPANはNEXT HEROを通じて、日本発のインクルーシブな雇用を実現する社会インフラ作りに挑戦しています。その理想実現のため、様々なセクターの皆様と就労困難者ゼロの未来実現に向けて議論を積み重ねていきたく、対談を連載しております。 今回はベストセラー『発達障害大全』(日経BP)の著者、黒坂真由子さんをゲストに迎え、発達障害のある方が生きやすい社会を実現するために不足していることや、「支える・支えられる」の境界を超え、発達障害支援における「つながり」の重要性などについてお話しいただきました。

ゲスト 黒坂 真由子氏
編集者・ライター
埼玉県川越市生まれ。中央大学を卒業後、東京学参、中経出版、IBCパブリッシングをへて、フリーランスに。ビジネス、子育て、語学などの書籍を手掛ける傍ら、教育系の記事を執筆。絵本作家せなけいこ氏の編集担当も務める。日経ビジネス電子版で「もっと教えて!『発達障害のリアル』」を連載。著書に「発達障害大全」(日経BP)などがある。短期連載「養老孟司と『死にたがる脳』」などを担当。
インタビュアー 小野 貴也
VALT JAPAN株式会社 代表取締役CEO
目次
「発達障害」という言葉の認知と、個々人の理解や行動にはまだ乖離がある
小野 貴也
(以下、小野)
今回ご登場いただくのは、『発達障害大全 ― 「脳の個性」について知りたいことすべて―』(日経BP)の著者、黒坂真由子さんです。どうぞよろしくお願いします。とても読みやすい本で、黒坂さんご自身の原体験も含めて、その世界に惹き込まれました。大作ですね。
黒坂真由子氏
(以下、黒坂)
本書は、「発達障害のことを何とか知りたい」と思い、始めたWeb連載をまとめたものです。発達障害という、定義がぼんやりとした概念を理解するためには、私にとってはこれだけの厚み、ボリュームの本が必要だったんだ、とあらためて感じました。
小野
黒坂さんのご経歴をおしえていただけますか。
黒坂
フリーランスで書籍の編集やライティングをしています。私は発達性読み書き障害の息子を持つ当事者でもあり、書籍だけでなく、雑誌やWeb媒体での連載も手がけています。主に取り扱うテーマは子どもの成長や発達、教育関連です。一時期、医療系出版社で校正をしていたことがあり、その影響で脳や医学に関する執筆も増えました。とくに脳の分野は進歩が早いので、新しい知見を発信することに魅力を感じていますね。また、英語教育にも興味があり、この分野の取材や執筆も行っています。

小野
まずお聞きしたいのですが、発達障害のある方が生きやすい社会を実現するために、「今、もっとも欠けているもの」は何だと思われますか? 私自身は事業を手がけて10年になりますが、欠けている部分がどうしても目につきます。時には、それが本当に欠けているのか、単にそう見えているだけなのかとわからなくなることさえあります。ただ、何かを充足させることで解決できる課題があると素朴に思うのですが、黒坂さんはどうお考えでしょうか。
黒坂
この本を出版した理由にもつながるのですが、もっとも欠けているのは、「発達障害に関する知識」だと思います。私自身も全く知識がなかったために、息子に対してもひどく当たってしまった経験があります。
息子は発達性読み書き障害があり、小学校1年生の頃、目の前の漢字を見ながら書き写すことができませんでした。そのことを私は理解できずに、「ちゃんとやりなさい」とか「よく見て」と注意し、叱ってしまう日々でした。でも、息子自身はちゃんと見て、ちゃんとやっているのです。努力しているのに、線が1本多かったり、縦横を間違えたりしてしまう。その時に足りなかったのは、息子の努力でも私の育て方でもなく、発達障害についての知識でした。
発達障害やディスレクシアだとわかったことで、注意するばかりではなく、どうやって勉強していったらいいのだろう、と方法論を考えるようになりました。そして、「叱る」から「一緒に頑張ろう」と対応が変わりました。私の人間性自体はまったく変わっていませんが、「知ったことで対応が変わった」という経験をしたのです。先程おっしゃった「足りているかもしれないけれど、足りていないように見えてしまう」ということでいうと、今の社会では「発達障害」という言葉自体は認知されていますが、それが実際の個々人の理解や行動に結びついているかというと、まだまだ分断があると思います。その認識と実態のギャップが、「足りているのか、足りていないのか」という問題を生んでいるのではないでしょうか。
小野
なるほど。「知識」は非常にヒントになるキーワードですね。知識は生活だけでなく、仕事や教育の現場でも重要になります。これまでの、黒坂さんの仕事と教育をつなぐ取り組みの中で、印象に残っている事例があれば教えてください。
黒坂
本書でも紹介した、中邑賢龍教授が主導する東京大学の先端科学技術研究センターに、LEARNというプログラムがあります。登録すると案内メールが届くのですが、2025年1月のプログラム案内で、「1週間の家出をして、アルバイト体験をする旅2025」という子ども向けのプログラムがありました。これは、居心地の良い家庭から離れて自分を見つめ直し、仕事とは何かを体験するもの。教育の一環ですが、仕事につながる要素が多く含まれています。「教育」と「仕事」の間は分断されがちですが、こうした取り組みはその橋渡しになると思います。個人的に懸念しているのは、やはり教育と仕事の間の分断です。そこをうまくつなげなければ、「(発達障害を持つ子も)学校にいる間はなんとかやっていけたけど、働きだしたら難しくなった」という状況を減らせると思います。こういった取り組みがもっとあるといいですよね。
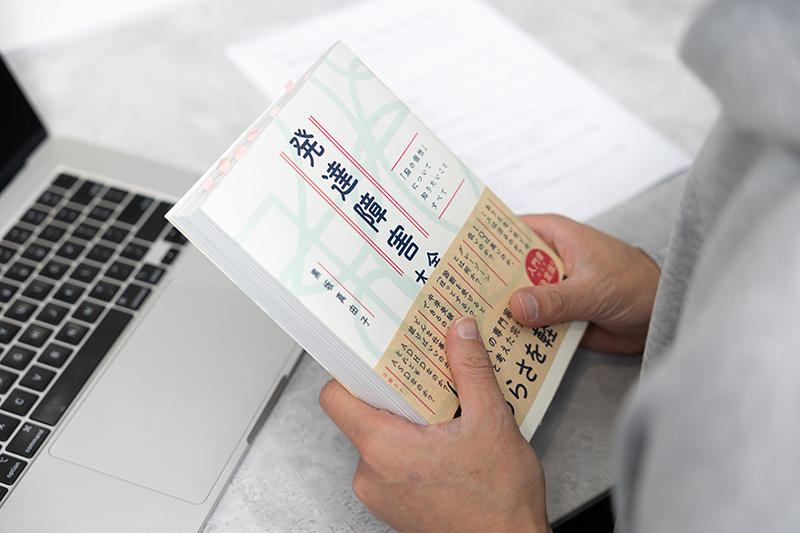
ICTを活用した学び方の多様化と課題
黒坂
また、ICTを使った学び方にも注目が集まっています。たとえば、LEARNとSoftBankが連携して行っている「魔法のキャラバン」というプログラムでは、ICTを活用して、子どもたちが自分に合った学び方を発見します。目からの情報が得意な子もいれば、耳からの情報を取り入れるのが得意な子もいるので、それぞれの得意分野に合わせた学びを提供できるのがICTの強みですね。ただ一方で、こうした試みはまだ少なく、多くの親が試行錯誤の末に苦労しています。たとえばディスレクシアの子どもを持つ親たちは、適切なICT機器を探すために時間もお金も費やしています。もっと手軽に試せる機会や支援があれば親の負担も減るはずで、このような取り組みが広がることで、子どもたちがより生きやすい社会を築けるのではないかな、と感じています。
小野
なるほど。小学校の先生の数など、「教育をする側が足りていない」という課題もあるのでしょうか。
黒坂
そうですね。以前は先生になるために、発達障害について学ぶ必要はありませんでした。でも今の時代では、先生になる方々が発達障害について学ぶ時間や、研修する時間をしっかり取るなどの準備も必要です。すでに先生のための研修は行われていますが、「割とさらっと終わってしまう」という話をよく聞きます。1時間の研修を聞いただけでは内容を理解するのは難しいですし、困っている子を見つけるという意味でも難しい。それ以前に先生が足りていないという問題もあります。そこも一緒に解決していかないと、子どもたちをじっくり見るのは難しいと思いますね。
小学校低学年の担任の先生が一人一人をじっくり見ることができれば、全クラスに特別支援の先生を配属する必要はないですし、きっと気づいてあげられることも増えるのではないでしょうか。先生が知識を得るのと同時に、先生の人数も増えて、働き方が変わっていく。そうなっていってほしいですね。
小野
先ほどの「1週間の家出を体験する旅」などはまさに参加型で、発達障害をもつ子どもたちの一人一人が、能動的に参加してスキルを身につけていく素晴らしいプログラムですね。そうやって知識も身につけていく機会があると、先生の数にだけ依存しない可能性があります。むしろ教育を受ける側のアップデートがどんどん加速していくというような、そういう流れにはなりそうですか。

黒坂
たとえば、公立学校の改革を待っていたら子どもが大人になってしまう可能性も十分あるので、いろいろなところで機会を提供してもらえたら、そこにつながる人も増えると思います。「どこが中心か」ではなく、学校、企業、地域など、あらゆる場所で、そういう場を作っていけるといいんじゃないかなと思います。
小野
黒坂さんのお話を踏まえて、「脳の個性」というお話に、少し戻りたいと思います。社会全体で脳の個性を認識するために整えるべき制度や仕組みについて、黒坂さんはどのようにお考えですか?
苦手の「早期発見」で子どもたちの未来が変わる
黒坂
一番欲しいのは全国的な読み書きのアセスメント制度で、読み書きが得意苦手というのを全国的にチェックする制度があるといいなと思います。
たとえば発達障害の中でADHDやASDは健診で見つかることが多いですが、ディスレクシアは現状見つかっていない子がたくさんいるはずなんですね。筑波大学元教授で、発達性ディスレクシア研究会理事長の宇野彰先生の統計によると、7〜8%の人が発達性読み書き障害の可能性があるそうです。クラスで2〜3人いる計算になりますが、実際に特別支援教育を受けている子は少ないです。
早期に見つけることで、タブレットなどを活用して対応すれば、障害ではなくなる可能性が高まります。それを見逃されてしまうことで、「ちゃんとやれ」と叱られたり、「自分は勉強ができないんだ」と思い込んでやる気をなくし、自己肯定感が下がったり、という二次障害が起きたりしてしまうんですね。
また、日本語は非常に多様な文字体系を持つ言語であり、障害がなくても苦手な子は潜在的にも多くいるはずです。そのサポートが「マイナス」ではないという認識を広めることも重要で、小学校1年生くらいで全国規模での検査を実施することで、早期発見・支援が可能になると思います。情報を得る手段として読み書きが重要視されている社会では、読めない・書けない子が能力を表現できず、評価されない問題があります。GIGAスクール構想などでICT環境が整備されているにもかかわらず、それを活用できていない現状を見ると、あと一歩の工夫が必要ではないでしょうか。
小野
確かにプロダクトやハードは進化していますが、AIなども出てきて、情報とそれらをどう使うかという、今度は「使い方大全」的なものが求められますね。
対談の後編では、
- 「支える・支えられる」という関係性に囚われない
- 発達障害支援における「つながり」の重要性
- 一方通行の関係性にならないために
について語ります。
当対談は音声でもお楽しみいただけます。下記のSpotifyよりご視聴ください。