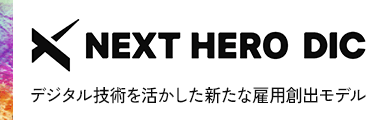第10回 【後編】「支える・支えられる」の境界を超えて

Road to IX
〜 就労困難者ゼロの未来へ 〜
編集者・ライター 黒坂 真由子氏
VALT JAPANはNEXT HEROを通じて、日本発のインクルーシブな雇用を実現する社会インフラ作りに挑戦しています。その理想実現のため、様々なセクターの皆様と就労困難者ゼロの未来実現に向けて議論を積み重ねていきたく、対談を連載しております。 今回はベストセラー『発達障害大全』(日経BP)の著者黒坂真由子さんをゲストに迎え、発達障害のある方が生きやすい社会を実現するために、何がもっとも不足しているのかや、実際に仕事に就く際に事前に経験しておきたい職業体験のお話など伺いました。

ゲスト 黒坂 真由子氏
編集者・ライター
埼玉県川越市生まれ。中央大学を卒業後、東京学参、中経出版、IBCパブリッシングをへて、フリーランスに。ビジネス、子育て、語学などの書籍を手掛ける傍ら、教育系の記事を執筆。絵本作家せなけいこ氏の編集担当も務める。日経ビジネス電子版で「もっと教えて!『発達障害のリアル』」を連載。著書に「発達障害大全」(日経BP)などがある。短期連載「養老孟司と『死にたがる脳』」などを担当。
インタビュアー 小野 貴也
VALT JAPAN株式会社 代表取締役CEO
目次
「支える・支えられる」という関係性に囚われない
黒坂
発達障害を持つ子どもの親御さんたちからよく聞くのは、「コーディネーター」や「コンシェルジュ」、あるいは「ソーシャルワーカー的な人」が欲しいという声です。
発達障害が疑われる時に、医療、教育、福祉など、まずどこにアクセスすればいいのか、「そこからもうわからない」と聞きます。地域に発達障害支援サービスが存在しても、それを知らずにつながれない問題がある。たとえば共通試験で配慮を受ける(1.3倍の時間が与えられる)ためには、支援を受けている証明が必要ですが、これを知らないと申請すらできない現状があります。
小野
そういった課題は、職場や仕事の現場でも、顕著に現れるように思います。「絶対に向かない」と誰が決めるのかという問題もありますが、向いていない仕事を避けることも大事だと思います。学びの場においてはどんなサポートが必要になると思われますか。
黒坂
専門家の方々の話を聞くと、発達障害の人が持つ傾向の一つとして、「自分がどういう人なのか分からない」ために、「だからこそ向いていないところに飛び込んでしまう」という傾向があるようです。そして私が思うのは、みんなと同じことがなかなかできないゆえに、「同じようにやりたい」という気持ちがとても強いなと感じることがあります。たとえば、息子が「公務員になりたい」と言った場合、親としては不向きだと感じても、小野さんがおっしゃるように「いや、絶対公務員なんか向かないからやめなさい!」というのは良くないので、職業体験を通じて、どういったことが自分に向いているのか、好きなのか、ワクワクするのかという経験をするのが一番いいのではないでしょうか。あるいは向かない仕事でも、試すことで「この方法だったらできる」という新しい発見が見つかるかもしれませんし、実際に「向いていない」と理解する経験になることもあります。

小野
私も事業をやる上で、大事にしてきたことがあります。それは、「転んでも大けがしない環境で、“失敗できる機会”を、仕事という世界で作りたい」ということです。やっぱり、誰もが失敗は嫌じゃないですか。怖いし、成功したいです。黒坂さんのおっしゃるような、「失敗してもいい環境」で職業体験できるような機会を増やせたら素晴らしいと思います。実際に作るとしたら、どんな環境になると思いますか?
黒坂
やはり体験の場所でしょうか。実際の仕事場に入らせてもらうのがいいのかなと思います。また、その現場で仕事に携わる機会があるとするなら、短期就労のようなスタイルがいいのでは、とも思いますね。なぜかというと、(本人は)ずっと続けるつもりなのに、「もう来なくていいです」と突然キャリアを切られてしまったら、ショックじゃないですか。なので最初から、3カ月とか、半年という形で就労して、雇用先と本人、双方がうまくいったら続けるようなしくみだといいですね。
小野
アメリカ・シアトルに拠点を置く障害者就労支援サービスを提供する非営利団体(NPO)のノースウエストセンターが、もしかするとそれに近いかもしれません。Amazonのロジスティックセンターでピッキングしたり、ラッピングをして発送したり、そういう仕事が経験できて、パートタイムの仕事として雇用された事例もあるそうです。
ここからは私の勝手な妄想ですけども、同じセンターの中にいろいろな企業の職業機会がセットされているといいな、とも思いました。「自分はピッキングじゃないな。レストランかな」など。これが一つのセンターにまとまっていると効率的だし、企業にとってもそこで得られるデータは採用活動のヒントになりますし、あるいは就職につながることが目的じゃなくてもいい。そういうセンターがあれば、「職場体験」を超えて、「自己発見」としての価値も提供できると思います。

黒坂
障害のあるなしに関わらず、利用したいと思う人は多そうですね。自分に何が向いているのかは、やってみないとわからないですから。
発達障害支援における「つながり」の重要性
小野
その点、最近の社会では、少し追い風を感じることもあります。たとえば、MicrosoftやGoogleが発達障害の方々を積極的に採用しているというニュースが以前話題になりました。企業のイノベーションに貢献する力を期待しての採用なので、否定するつもりはないのですが、実際に黒坂さんから見ると、発達障害を持つ方の視点や能力は、企業のイノベーションにどのように貢献できると感じておられますか。
黒坂
そうですね。ただ、その期待は、時に負担になることもあると思います。発達障害の方が特別な能力を持っているとか、天才だと決めつけられるのもプレッシャーになりますよね。実際には、多くの人が普通の能力を持っていて、特別な能力がある人は発達障害に限らないですし。
ただ、発達障害の方が働きやすい職場を作る努力をすることで、結果的には誰にとっても働きやすい環境が整うと思うんです。そういった職場では、対話を重ねることで新しいアイディアが生まれやすくなる。イノベーションというのは、一人の天才が考えつくものではなく、多様な視点が交わるところから生まれると思うんです。たとえば、今までは同じ能力の人しか職場にいなかったとしたら、そこに新しい考えを持つ人、違う考え方や体験をしてきた人が入ることで、お互いの知識の交換が生まれて、新しいことも生まれる。なので、運営する側が、組織を変えることが第一歩ではないでしょうか。
たとえば、「アライシップ」という取り組みがあります。「アライ」は「結びつける」という意味です。外資系企業では、発達障害を持つ人だけではなく、LGBTQの人のようなマイノリティなど、少数者の人を支えていくコミュニティをサポートしている取り組みがあります。そのグループでは、発達障害の当事者であったり、発達障害を持つ子どもを育ててきた親が、「こういう時はこんなふうに対処するといいよ」「制度を変えるともっと楽になるよ」ということを話し合っていく活動をしています。そういうコミュニティがあると困りごとも話しやすくなるし、「(自分たちは)こういうサポートがあって助かったよ」といった情報をシェアしやすいですよね。
そういったいろんなグループがあるので、発達障害においてはサポートされる側であっても、他のグループでは自分がサポートする側に回ることができます。「常にサポートされる」だけではないグループ作りができるというのは、とてもいいことだなと思いますね。

一方通行の関係性にならないために
小野
「支える・支えられている」というのは日常生活の中で必ず起きているはずですが、目に見えづらいというか、感じづらいですよね。そこがより見えやすい社会になると、人に優しくなれるし、1日1日が少し穏やかに生きられる気がします。黒坂さんのお話を聞いて肩の荷が下りました。
というのは、何かを「サポートしている」と思えば思うほど、果たしてそれが本当に正しいのかというと、正しくない結果が出ることもあります。僕の場合は事業を通じてですが、創業当時は期待に応えられなかった経験もありますし、その逆も然りで、「自分は支えられてばっかりだな」と思って辛くなることもありました。お話を聞いていて、あえて「支える・支えられる」というわかりやすい環境、機会に出会えるのはとてもいい経験になりますし、忘れかけていた大事なものを再発見できるような気がしました。
黒坂
支える側の方も、大変だと思うんですよね。この本の元になったWeb連載をしていたときにも、「当事者よりも、周りの人が大変なんです」という反応があって、それには本当に共感しました。
でも、本人も大変ですし、周りも大変。だから双方が「サポートしなきゃ」「自分はサポートをずっとされる側なんだ」と、そういう関係性になっていく一方なのは、つらいことだと思います。いろんな場面で支えることもあれば、支えられることもある。そこを意識するということですよね。私自身も、息子をサポートしているつもりでいましたけれど、それこそ自分の「書く」というキャリアにおいては、とてつもなく大きな体験で実は支えられて、この本が出来たわけです。ですから、支えているつもりでも、支えられていた、ということはあらゆる世界であると思います。
小野
黒坂さんのお人柄を知って、また本を読み返したくなりました。この本には、黒坂さんや専門家の方々の想いが詰まっていて、多くのキーワードがちりばめられていますので、続きはぜひこの著書をお読みください。
黒坂
キーワードを知っておくだけでも十分です。それを必要なときに思い出して調べたり、活用したりすることで役立てていただけたらと思います。
小野
ありがとうございます。本当にあっという間に時間が過ぎましたが、最後に何かメッセージをいただけますか?
黒坂
そうですね。もし今、つらい気持ちを抱えている方がいらっしゃったら、周りに話したり、本を読んだり、つながることで何かが変わると思います。「支えてくれる人は必ずいますので、大丈夫ですよ」と言いたいですね。
小野
黒坂さん、心に染みるメッセージをありがとうございました! 皆さん、次回の「Road to IX、就労困難者ゼロの未来へ」もお楽しみに。
当対談は音声でもお楽しみいただけます。下記のSpotifyよりご視聴ください。